
『光りかけてやめたすべての星たちへ 大宗掌短編集』
- 新刊
- 成人向
- 大宗
- B6
- 134p
- 会場頒布のみ
・2026年1月25日発行
・東雲大和×巻宗介の掌短編集
・モブ視点、年齢操作(妙齢/同棲)あり
・掌編によっては大宗成分がほぼないものもあります
・サンプルは収録作品一覧(目次)、全年齢作品1作品を掲載しています
・「共喰いの夜」は以前オンラインイベントで展示した作品の再録です
・サンプルは収録作品一覧(目次)、全年齢作品1作品を掲載しています
エピグラフ及び収録作品目次
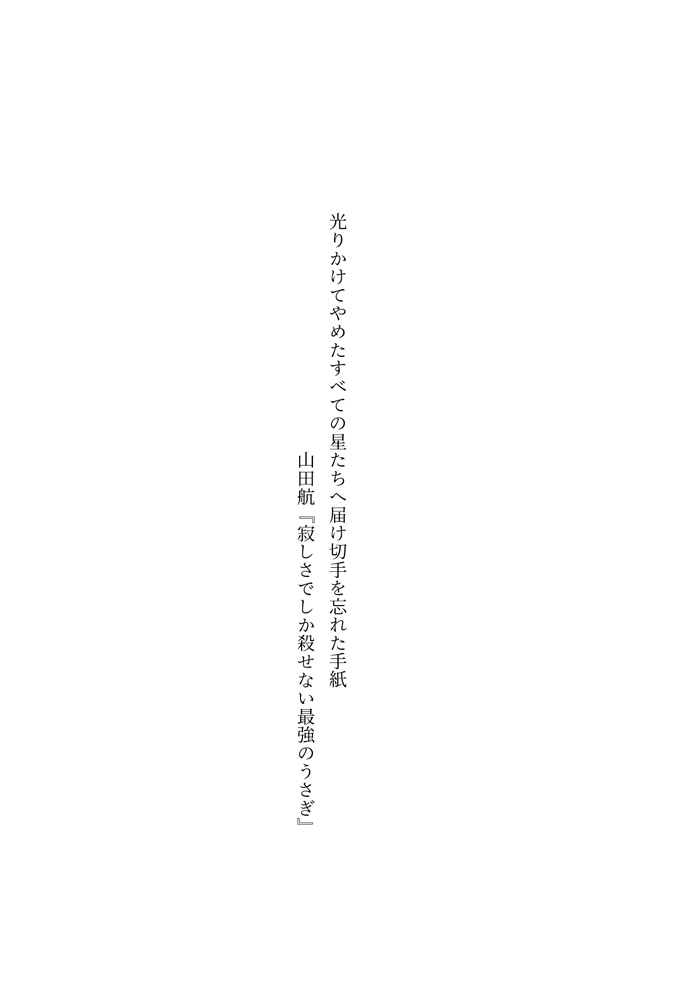
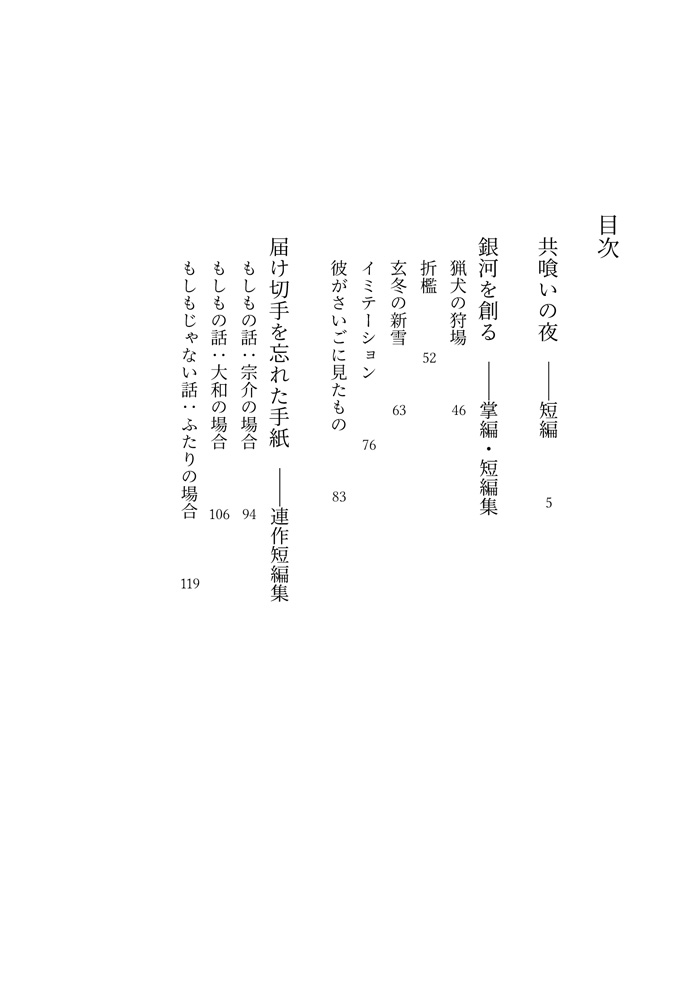
全年齢サンプル(「もしもの話:宗介の場合」全文)
犬と暮らしている。飼っている、のではなく、暮らしている、という表現が宗介にはしっくりくる。
雑種の、中型犬と大型犬の間くらいの犬だ。日本犬がベースだろうけれど、洋犬の血も混じっている気がする。ふかふかとした毛並みに、黒いけれどどこか青みがかった目。引き取った直後に連れて行った動物病院ではまだ若い犬だろうと言われたけれど、宗介にはときどき、この生きものは自分よりも長い年月を生きているのではないか、と思うときがある。
――例えばこんなとき。
「う、」
冷たく湿った鼻先が宗介の額をぐいっと押した。それで意識が浮上して、自分が眠っていたことに気付かされる。犬によって起こされたのだということも。
「……ンだよ……このクソ犬……」
宗介が寝起きの不機嫌さで睨みつけても、宗介の飼い犬は静かに飼い主を見下ろしている。宗介が目覚めると頭を上げて端座の姿勢に切り替えるあたり、じゃれついたのでもなく構ってほしがったのでもなく、ただ宗介を起こすために鼻先を押し付けてきたのだと分かる。その様子を見ながら、宗介は思う。犬ってこんなもんなんだっけ。
――こんな、分別があるというか、本能以外の道理で動いていそうな、そんな気配のする生きものだっけ。
ついさいぜんまで突っ伏していたローテーブルの上、広げた作曲用ノートと資料の山に再度頭を落として、居眠りを妨げられた不満に「あー」とため息をつく。自分のその振る舞いのほうが犬よりよほど動物めいている気がする。
犬は静かに宗介を見下ろしている。紺青、に近い黒い瞳は、宗介にこう問いかけているようにも思える。こんな場所で寝落ちしたら、人間は――宗介は風邪を引くんだろう。ちゃんと寝床で寝ろよ。
宗介の幻聴だ。想像だ。けれど、ただただじっと見つめてくる犬の双眸には、そう感じさせてしまう何かがある。何か。老成した年長者のような。未熟な若者をそっとたしなめているような、何とも言い難い、何か。
「……分かったよ、ったく……」
犬の無言の訴えに従って、宗介はゆっくりと立ち上がった。確かにおかしな体勢で居眠りしていたから身体が凝っている。時間を確認すると二十二時過ぎ。――翌朝が早いことを考えると、今日はもう仕事は切り上げて眠ったほうがいい。
風呂に入るべきか、と考えかけるけれど、いっしょに四肢を上げた犬がまっすぐ寝室のほうに向かったので、どうやら風呂は不要のようだ。――これもまた不思議なことに、身体を温めたほうがよさそうなときは犬は寝室ではなく浴室に宗介を引っ張っていこうとする。
犬が宗介のコンディションを把握していて適切な選択肢を示している、なんて、他人に話してもぜったいに信じてもらえないだろう。分かっているから誰にも話したことはない。けれど、でも、そうだろう、と思い込みたくなる程度には、犬の振る舞いは泰然としていた。人間の物差しで測ってはいけない生きもの、みたいな。
(いや、犬は犬だろ)
――そうは思うものの、宗介の飼い犬が、宗介の想像するところの犬めいた行動をすることはほとんどない。何なら初めて会ったときがいちばんコイツは犬っぽかった。
数年前のことだ。
犬は、空に向かって切実に吠えていた。威嚇や興奮の吠声ではなく、長く厚い遠吠えだった。繰り返し繰り返し、何度も声を上げていた。
夕暮れが近い初夏の日だった。
仕事からの帰り道、自宅に近付くにつれその声は大きくなり、つまり音の発生源は宗介の家に程近いのだと分かったとき、宗介は駆け出していた。声のほうへ。
だって、誰かを呼んでいる声だ、と思ったのだ。言葉は分からないけれど声に滲む必死さは伝わった。
離れた場所にいた宗介にすら聞こえたその声は、遠く、まで届くように、叫んでいた。遠く、できる限り遠く。届く距離を最大限に。誰か一人にでも、この声が響くように。
犬がいたのはある一軒家の庭先で、宗介が駆けつけたとき、近隣住人も何人かがその家の周囲に集っていた。彼らは犬の声がやかましくて辛抱ならず、騒音だ、さっさと黙らせろと家主に文句を言おうとしているところだった。
――犬はよく吠えるのか、と隣家の住人らしき人間に聞いたところ、いや、初めて聞いた、と首を振った。それで宗介は確信した。
この犬はやはり、誰かを呼ぶために、声を上げている。
玄関を横切って、吠える犬の元に向かった。庭も不法侵入になるんだっけ。少し気になりはしたものの、それ以上に犬の切迫さが気になった。
『何を必死に訴えてるんだ、テメエは』
宗介の言葉を理解したわけでもないだろうに、犬は途端に吠えるのをやめて、庭に面した掃き出し窓に駆け寄った。つられて宗介も窓のほうを見る。カーテンが半端に引かれていて、窓の向こう側に手が見えた。――倒れている、人間の手が。
そこからはビデオの早回しのようだった。救急車が呼ばれ、昏倒していた家主は病院に運び込まれた。その顛末は、独居老人が飼い犬のおかげで一命を取り留める、と地方ニュースで取り上げられたとか何とか。
けれど、命は助かったものの、老人は犬の待つ家に帰ることはできなかった。
元通りの回復は見込めず施設に入らざるをえない、犬の引き取り手を探している、もし叶うならあの犬の終生の飼い主になってくれないか、と老人から懇願されたとき、宗介は自分でも驚くほど素直に「他に行き場がないなら」と答えていた。赤の他人の、何の義理もない頼みにどうして応じたのか。老人に同情したのではない。犬という生きものが好きだったわけでもない。そもそも宗介は人間も含めて生きもの全般が苦手だ。いま住んでいる家――実家だって、母親が死んで住む人間がいなくなったから使っているのであって、母親が存命だったら宗介は未だにマンションで一人暮らしをしていただろう。
借家ではないことも決断の後押しになったのかもしれない。けれど、とにかく、宗介は犬と暮らし始めた。この犬でなければ選ばなかったであろうことも、確かだった。
老人の命を救ったときに初めて近隣住民がその声を聞いたという話の通り、犬は宗介の家でもまったく吠えなかった。老人によく躾けられたのか、手のかからない犬だった。遊びたいときは一匹で適当におもちゃを転がしているし、餌を催促することもほとんどない。老人の家から宗介の家に連れ帰ったときも、特に困惑する様子もみせず、室内を見渡したあとにじっと宗介を見上げた。今日から俺は、ここで暮らすのか。黒と青を混ぜ込んだ両目がそう問いかけているようだった。無言で頷くと、犬はそれだけでぜんぶを理解したかのように、ソファの近くを自分の居場所と定めてごろりと身を横たえた。
やはりどこか、犬というよりは犬の姿かたちをしているだけの別の生きものみたいな振る舞いだった。
犬は宗介との暮らしにすぐに馴染んだ。まるで子犬の頃から――宗介が十代の子どもだった頃からいっしょにいるような、そういうふうに錯覚しそうになるくらい、犬がそばにいることは自然に感じられた。
――守られている、ように感じることさえ。
宗介が自宅で作詞作曲の仕事をしているとき、犬は大抵宗介のすぐそばに横たわってじっとしている。遊びを要求することも餌を欲しがることもなく、ただ静かに、宗介がときどき奏でるギターの音や歌声に耳を澄ませている。
そうして宗介が煮詰まると、気を紛らわせようとでもするかのように、宗介の太ももにぽすんと顎をのせてきたりする。まあまあ、焦るなよ。ここまでの音色、俺、好きだぞ。――そんなふうに言っているようにさえ、見える。
おまえは気楽でいいよな、と笑いながら軽く額や頭を撫でてやると、ごろごろと機嫌良く喉を鳴らす。その、他に類を見ない独特の音を伴奏にBLASTの曲を適当に歌うと犬はいっそう上機嫌になる。尾がゆらゆらと揺れるのを見るうちに不意に新しい音色を思い付いたりもする。BLASTのギターボーカルとして活動して十数年、犬と暮らし始めて三年と少し。犬のいない生活のほうが犬のいる生活よりはまだ長いはずなのに、宗介は犬と暮らし始める前に自分がどんなふうに曲を作っていたかをもう思い出せない。
夜、ひとりでどう眠っていたかさえ。
(……あたたかい)
犬は宗介にべったりと甘える素振りは見せない。けれど眠るときだけは宗介のそばにいたがる。毛布の中に潜り込むときもあれば、宗介の足元近くで丸まって眠るときもある。どう眠るかはその日の犬の気分次第のようだけれど、宗介のすぐそば、という条件だけは変わらない。
自分以外の生きものが、静かに寝息を立てて、自分といっしょに眠っている、という実感が、こんなに心地いいものなのだと、宗介は犬と暮らして初めて知った。――だからといって、それなら犬ではなく人間ならもっと心地いいだろう、とは思わなかった。犬だけでじゅうぶんだった。この犬の不思議に落ち着く気配と体温だからこそ心地いいのであって、人間にそれが与えられるとも思えなかったし、与えてほしいとも思わなかった。この犬だからいい。
犬に寝室に引っ張っていかれるのにもすっかり慣れた。――というより、それが宗介の日常になった。今夜もそうだ。仕事をしながらうたた寝すると、犬は必ず宗介を揺り起こす。起こして、軽く宗介のスウェットの裾を咥えて引く。なあ、宗介、そんなところで寝るなよ。あっちの、ふかふかであったかいやつ、あそこで寝るのが気持ちいいだろ。いっしょに寝よう。強引ではないけれど有無を言わせない犬の要求に、はいはいと応えて今夜もベッドに潜り込んだ。宗介の腰のあたりに寄りかかる犬の頭を撫でてやっているうちに眠っていた。今夜も温かかく、心地良かった。
――そうして、まだ外も暗い時間に、犬は起き上がって宗介にぐいぐいと頭を押し付ける。宗介の就寝も起床も、完全に犬に掌握されてしまっている。
くう、きゅう、と憐れみを誘う声で犬が小さく鳴く。起きろ、起きてくれよ、宗介。
なあ、俺、散歩行きたい。
「あー……ったく……。毎日毎日飽きねえなあ、てめえ」
のそのそと、観念して宗介も起きる。春の夜明けは案外遅い。けれど、そうはいっても時刻はまだ五時前。犬と暮らし始める前の宗介だったらむしろ入眠の時間帯だ。健康的にも程がある。
ううん、と伸びをして宗介が覚醒する間にも、犬はすっかり目覚めてベッドから降り、宗介が動くのを今か今かと待ち構えている。
一日のうちで、犬がいちばん目を輝かせる時間だ。人間も犬も、期待にわくわくする瞳の形は同じらしい。
犬の眼差しに急かされるようにして準備をして、ひとりと一匹で家を出た。やはりまだ暗い。けれどもう、夜明け前の暗い道を行くのにもすっかり慣れた。深夜に向かって更けていく夜と、朝を迎える明け方近くの夜の色は違う。朝が近い夜の色は、犬の瞳の色にどこか似ている。
――犬らしい振る舞いも、何かへの強い執着もなさそうな犬だけれど、唯一、夜明け前の散歩だけは欠かさない。毎朝ランニングをするストイックなスポーツ選手みたいに、犬は朝が近付くたびに宗介を催促して散歩に出かける。
機嫌よくふりふりと左右に揺れる尻尾を前方に見ながら宗介は笑う。そんなにいいもんか、明け方の散歩って。まったく、付き合わされるこっちの身にもなってみろ。二十二時台に眠るなんて――夏場は更に早くなる――おまえと暮らさなかったら絶対に定着しなかっただろう生活習慣だ。
もしコイツが人間だったら、一人で勝手に起きて勝手に散歩なりランニングなりにも行っただろうに。犬だから俺が付き合わざるをえない。そんなことを考えて、ふと思う。俺は、コイツが人間でも、いっしょに暮らしていいと思っているのか。
他人の体温が、――肉親の体温ですら苦手で、だから一人で生きてきた。犬は唯一その境界線を越境してきた存在だった。それはコイツが人間ではなく犬だから、だと思っていたけれど、案外、同じ人間でも悪くなかったかもしれない。人間だとコイツの体温はどうなるだろう。宗介よりはまあ温かいだろう。
益体もなく考えているうちに、東の端がしらじらとしてくる。空の大半はまだ夜の色をしている。夜明けの一歩手前、――犬の瞳の色にも似た、群青の空。
(東雲――しののめ)
夜明け前の空をそう呼ぶのだという。しののめ。日常生活では決して使わないだろう音なのに、不思議に心地いい響きだった。犬の体温と同じような。
ぐい、と犬が前進の勢いを増す。朝日が待つほうへ駆けていこうとする。引っ張られながら宗介は犬をたしなめる。
「こら、あんまり急いで走るなクソ犬――大和」
犬――大和と名付けられた宗介の相棒は、振り返って尻尾を振ってみせた。行こう、宗介。俺、あっちに行きたい。明るいほう。夜の終わるほう。
わん。犬は宗介を呼ぶように軽く吠える。家では決して吠えない犬が、朝日の前ではときどきこうして声を上げる。澄んで真っ直ぐな鳴き声。本気を出せば遠くにいる宗介にだって届く、ほんとうは声量も呼ぶ力も持っている、宗介の犬。
この犬が、と、ときどき思う。
この犬が、人間だったら、どんな声で、どう歌っただろう。
その声は、あの日、宗介を呼んだように、宗介の心を強く打つだろうか。
――あり得ないことを想像したところで詮無い話だ。けれど、何となくだけれど、打つのだろう、と思う。
おまえは。どんな姿かたちをしていても、俺を呼んで、明るいほうに連れて行こうとするのだろう。いっしょに行こう、と、並んで走ろうとするのだろう。
夜が明ける。東の空から光が射す。
真っ直ぐ伸びてきた逆光に、宗介の犬の姿が潤んだように滲む。
一瞬、ほんとうに一瞬だけ、犬のシルエットに、人間の影が重なったように見えた。
大きな背。茶色い髪。真っ直ぐ上に伸びた手は天を指している。もう片方の手にはマイクが握られている。――その隣で、ボーカリストを見つけた宗介が、ギタリストとして、ギターを鳴らしている。
ふ、と目を細めて逆光をやり過ごすと、犬が小さく首を傾げて立ち止まっていた。どうしたんだ、宗介?
何か見たのか?
「……なんでもねえよ」
笑って、大和に並んで歩いた。もしもの話。願望の話ではない。俺にはこの犬がいい。
それでも、そう、どこか別の場所で、この犬によく似たボーカリストを見つけている自分がいたとしたら。
それはそれで、きっと愉快な人生だろうと、宗介は思うのだ。
-----------------------
サンプルはここまでです
-----------------------